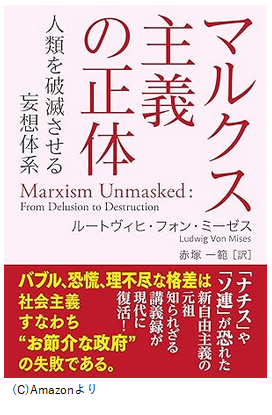先に書籍から引用。感想は記事下。 引用文 アテナイの有名な政治家のペリクレス、ペルシャ戦争の英雄テミストクレスなどは、プラトンによれば、どうにもならない迎合屋になります。アテナイのもっとも誇りとする政治家たちを、プラトンはそれこそぼろくそに批判するわけです。彼らは人々に一時的な快楽を与えることや、欲望を一時的に満足させることにこれ努めて、本当の政治とは何をなすべきかをまったく知らなかったというのが、プラトンの見方です。なぜかというと、彼らは哲学をしなかったからである。単純化していえば、ソクラテス流の哲学をしなかったという点をプラトンは指摘します。 それでは、本当…
『グノーシス~古代キリスト教の異端思想』(筒井賢治著,講談社選書メチエ) より引用 にもかかわらず、正統多数派教会は、正典の内容的な統一性には目をつぶり、ひいては教義の一貫性を犠牲にしてまでも、伝統にしたがって現行の二七文書をそっくり飲み込んだ。マルキオンは、福音の純粋性にこだわって伝承を選別し、なおかつテキストのレベルでも取捨選択をおこなった。それによってマルキオン聖書が成立し、マルキオン派教会が立ち上がった。しかし、この運動は長続きせず、西方ではおそらく五〇年程度しかもたなかった。他の二世紀のキリスト教流派、ウァレンティノス派やバシレイデ―ス派も、規範的な文書集…
権利=法(レヒト)の目標は平和であり、そのための手段は闘争である 。権利=法が不法による侵害を予想してこれに対抗しなければならない限り――世界が滅びるまでその必要はなくならないのだが――権利=法にとって闘争が不要になることはない。権利=法の生命は闘争である。諸国民の闘争、国家権力の闘争、諸身分の闘争、諸個人の闘争である。 世界中のすべての権利=法は戦い取られたものである。重要な法命題はすべて、まずこれに逆らう者から闘い取られねばならなかった。… イェーリング『権利のための闘争』(村上淳一訳/岩波文庫)、力強く惹き込まれる冒頭文。 平和のための闘争※が必要だという宣言…
ネットにしてはめずらしく共感できる、秀逸な記事だなと思って読んでいたら齋藤孝氏だった。 ⇒「本から学ばない人」と「読書家」の致命的な差 昔、この人の『読書力』という本がとても偏った内容で、全く共感するところがないと思ったのだがこの記事はいい。 旧制高校の学生が使った言葉で「沈潜(ちんせん)する」というものがありました。自己研鑽すること、自分を磨くことを「沈潜する」と表現したのです。とてもいい言葉だと思います。 忙しい毎日、膨大な情報洪水に流され浮遊するのではなく、「沈潜する」時間を持ちたい。本を読んで著者と一対一で対話する。あるいは自分自身と対話する。作品の本質に迫り…
『ガラス玉演戯』ヘッセ著、高橋健二訳。復刊ドットコム版より。 久しぶりのヘッセで、まだ冒頭ながら衝撃を受けた箇所。 「ああ、ものごとがわかるようになればいいんですが!」とクネヒトは叫んだ。「何か信じられるような教えがあればいいんですが! 何もかもが互いに矛盾し、互いにかけちがい、どこにも確実さがありません。すべてがこうも解釈できれば、また逆にも解釈できます。世界史全体を発展として、進歩として説明することもでき、同様に世界史の中に衰退と不合理だけを見ることもできます。いったい、真理はないのでしょうか。真に価値ある教えはないのでしょうか」 彼がそんなにはげしく話すのを、名人は…
本棚の整理中に発見したメモ。 何の本を読んでいる時にメモしたのか忘れたが、たぶん哲学関連のガイド本。 西洋では、「神は自由」と定義したいために「一切は偶然」「個人は自由」という思想が生まれた。 ※神は普遍に縛られない。だから人間個人と神を切り離し、人間の知覚から「普遍」を創り出さなければならない。そのような考えから形而上との決別――「オッカムの剃刀」が生まれた。近世哲学の源流。
Search
Sections
Trending now